教員一覧 (2025.4.8更新)
未来共生学
共生の人間学
- 斉藤弥生
(Yayoi SAITO) - 中井好男
(Yoshio NAKAI) - 近藤和敬
(Kazunori KONDO) - 佐藤桃子
(Momoko SATO) - 藤川信夫(兼)
(Nobuo FUJIKAWA) - 山崎吾郎【兼】
(Goro YAMAZAKI)
共生行動論
共生社会論
グローバル共生学
国際協力学
地域創生論
コンフリクトと共生
共生学系共通
※(兼)は本研究科内兼任を示す。【兼】は他部局教員等の本研究科兼任を示す。
未来共生学
共生の人間学
斉藤弥生 Yayoi SAITO

| 研究概要 Research |
【比較福祉研究】政府、市場、家族や地域の役割を踏まえ、支援を必要とする高齢者、障がいのある人たちが自立して生活できる社会、安心して暮らすことができる社会のあり方を研究する。(国際比較ではスウェーデンやノルウェーなど北欧社会、近年はドイツ、韓国における地域包括ケアと市民参加の研究に力を入れている。)
【地域福祉研究】福祉事業の多くは慈善事業として始まり、行政の事業と担われてきた。今日では市民の関わりなしでは、福祉サービスの展開を考えることはできない。社会福祉における住民参加(政治的参加、経済的参加、社会的参加)や当事者参加のあり方、ボランティアの意義を研究する。近年では特に、コ・プロダクションの概念をもとに、協同組合による介護と医療の提供が生み出す社会的価値についての研究に力を入れている。 |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
社会福祉学(高齢者介護、地域福祉、北欧型モデル、障がい者支援) |
| 研究キーワード Research Keywords |
高齢者介護、障がい者支援、スウェーデン、ドイツ、地域福祉、協同組合、社会的企業 |
| 主な担当科目 Classes Taught |
福祉社会論 |
| 代表的な著作 Major Publications |
・斉藤弥生&ヴィクトール・ペストフ(2023)『コ・プロダクションの理論と実践―参加型福祉・医療の可能性』大阪大学出版会
・斉藤弥生&小松理佐子(2023)『地域福祉の課題と展望』放送大学教育振興会 ・斉藤弥生&石黒暢(2019)『新・世界の社会福祉:3 北欧 スウェーデン/デンマーク/ノルウェー/フィンランド』旬報社 ・斉藤弥生&石黒暢(2018)『市場化のなかの北欧諸国と日本の介護:その変容と多様性』大阪大学出版会 ・Saito, Y. (2018) Has the long-term care insurance contributed to de-familialization? Familialization and marketization of eldercare in Japan. Christensen, K. & Pilling, D. Handbook of Social Care Work in the World. pp241-255, Routlege. ・斉藤弥生(2014)『スウェーデンにみる高齢者介護の供給と編成』大阪大学出版会(※第16回損保ジャパン記念財団賞) ・Campbell, J.C., Edvardsen, U., Midford, P., & Saito, Y (eds.) (2014) Eldercare Policies in Japan and Scandinavia: Aging Societies East and West. Palgrave Macmillan. ・Saito,Y., Abe Auestad,R. & Waerness, K. (eds.)(2010) Meeting the Challenges of Elder Care: Japan and Norway, Kyoto University Press and Trans Pacific Press. |
| より詳しい情報 More information |
● 斉藤弥生(2011,2013―)「高齢者福祉の課題」『NHKテキスト社会福祉セミナー』 ※NHKラジオ第2放送 土曜日午後7:00-7:25(再)日曜日午後0:15-0:40。 ※NHKラジオホームページ「NHKラジオ☆らじるらじる」http://www.nhk.or.jp/radio/でも視聴可能. ● 斉藤弥生&小松理佐子(2022―)『地域福祉の課題と展望』放送大学放送授業(全15回)※BSチャンネルで放映。 ● 研究内容の詳細については、大阪大学大学院人間科学研究科「福祉社会論研究室」のホームページをご覧ください。 https://welfare.hus.osaka-u.ac.jp/index.html |
中井好男 Yoshio NAKAI

| 研究概要 Research |
私が現在取り組んでいるのは、人間の活動を阻害する障壁や障害とそれらを乗り越えた先にある共生を考える質的研究です。その切り込み方には様々な観点がありますが、私は特に、ことばやことばの活動に注目し、その活動が生み出す障壁や障害にまつわる、他者、あるいは自身の経験を描くことを通して、共生社会の実現に向けて乗り越えるべき社会的課題を洗い出すとともに解決の糸口を探しています。
共生は人と人の間に生まれるものであり、そこにはことばによる対話があります。そして対話は他者理解を通した自己理解と自己変容をもたらすだけではなく、相互理解へと導いてくれる可能性も秘めています。共生の原動力であるとも言えるこの対話をもとにした研究や実践を通して、多様性を理由とした障壁や障害と共生という言説の記述を行なっています。 |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
応用言語学 障害学 共生学 |
| 研究キーワード Research Keywords |
ことば、ディスアビリティ、対話、マイノリティ |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・共生の人間学Ⅰ ・共生の人間学特講Ⅰ |
| 代表的な著作 Major Publications |
・中井好男(2018)『中国人日本語学習者の学習動機はどのように形成されるのか:M-GTAによる学習動機形成プロセスの構築を通して見る日本語学校での再履修という経験』ココ出版
・八木真奈美、中山亜紀子、中井好男(編)(2021)『質的言語教育研究を考えよう!―リフレクシブに他者と自己を理解するために』ひつじ書房 ・中井好男・脇坂真彩子(2021)「アプリやウェブサイトを活用した日本語学習」青木直子、バーデルスキー・マシュー(編)『日本語教育の新しい地図:専門知識を書き換える』ひつじ書房、pp. 201-221 ・中井好男(2022)「コーダである私に映る共生とプロフィシェンシー」鎌田修(監修)・鎌田修・由井紀久子・池田隆介(編)『日本語プロフィシェンシー研究の広がり』ひつじ書房、pp. 31-45 ・中井好男・キャサリン ソーントン(2021)「多様な地域語のトランスランゲージングとL2アイデンティティ―日本国内を移動するL2日本語使用者との語り合いから―」『第二言語としての日本語の習得研究』24、pp.30-47 ・中井好男(2021)「私はコーダとして日本手話を継承すべきだったのか―中国出身のコーダとの対話的自己エスノグラフィー」『言語文化教育研究』19、pp. 52-73 ・中井好男・丸田健太郎(2022)「音声日本語社会を生きるろう者家族の生きづらさ―見えないマイノリティによる当事者研究」『質的心理学研究』21, pp.91-109 |
| より詳しい情報 More information |
研究者総覧:http://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/37ac1dbde0f08f72.html
Researchmap:https://researchmap.jp/nakayoshi |
近藤和敬 Kazunori KONDO

| 研究概要 Research |
研究のテーマ:自然科学、哲学、芸術などの人間の諸活動を、人間の社会性を基盤として理解するための基礎的理論研究
研究の一般的背景:人新世時代とも言われる現代社会の諸問題の多くは、経済や社会、あるいは人間のモラルや自然科学など、通常は区別される領域が複雑に絡み合っている場所において生じています。たとえば環境問題はその典型例でしょう。このような現代の諸問題に取り組むためには、人間、自然科学、社会、経済という四つの基本カテゴリーのあいだの複雑なありようを、一貫した視野のもとで総合的に理解する新たな思考枠組みを構築する必要があると考えています。 Research topics: basic theoretical research to understand various human activities, such as natural science, philosophy and art, on the basis of human sociality. General background to research: many of the problems of contemporary society, also known as the Anthropocene era, arise where usually distinct areas, such as economy, society, human morality and the natural sciences are intricately intertwined. Environmental problems, for example, are a typical instance of this. In order to approach these contemporary problems, we believe it is necessary to construct a new framework for thinking that comprehensively understands the complexities between the four basic categories of human beings, natural science, society and the economy from a coherent perspective. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
哲学、現代哲学、フランス哲学、科学認識論 Philosophy, Contemporary Philosophy, History of French Philosophy, Scientific Epistemology |
| 研究キーワード Research Keywords |
社会性、科学、数学、芸術、構造主義 Sociality, Science, Mathematics, Arts, Structuralism |
| 主な担当科目 Classes Taught |
共生の人間学Ⅰ、共生の人間学演習 Philosophical Anthropology in Kyosei |
| 代表的な著作 Major Publications |
・近藤和敬『ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する――〈内在の哲学〉試論』講談社、2020年.
・近藤和敬『〈内在〉の哲学へ――カヴァイエス、ドゥルーズ、スピノザ』青土社、2019年. ・近藤和敬『数学的経験の哲学――エピステモロジーの冒険』青土社、2013年. ・近藤和敬『構造と生成Ⅰ――カヴァイエス研究』月曜社、2011年. |
| より詳しい情報 More information |
https://researchmap.jp/kazunorikondo |
佐藤桃子 Momoko SATO

| 研究概要 Research |
社会福祉学の視点から、子どもと家族が幸せに暮らせる地域社会のあり方や福祉的な支援について研究しています。主な研究フィールドは北欧デンマーク、また日本では山陰地方でもフィールド調査を行っています。デンマークの社会的養護における当事者参画の仕組みやボランタリーな実践、日本の子ども食堂など子どもたちを対象とする地域福祉活動に関心があります。子どもを対象とするソーシャルワーク実践については、デンマークだけでなく北欧諸国や欧州のその他の地域にも関心を持って比較研究を進めようとしているところです。
From the perspective of social welfare studies, I research the ways in which children and families can live happily within their communities, as well as the types of welfare support that can help achieve this. My primary research fields are in Denmark in Northern Europe, and I also conduct fieldwork in Shimane, Tottori. I am particularly interested in mechanisms for user participation in Denmark’s out-of-home care system and voluntary practices, as well as community-based welfare activities for children in Japan, such as children’s cafeterias. Regarding social work practices targeting children. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
社会福祉学、子ども家庭福祉
Social Welfare Studies, Child and Family Welfare |
| 研究キーワード Research Keywords |
子ども、地域福祉、ソーシャルワーク、NPO、社会的養護、デンマーク
Child and Family Welfare, Community Welfare, Social Work, NPO, Child Protection Services, Nordic countries |
| 主な担当科目 Classes Taught |
福祉社会論、共生学実験実習 |
| 代表的な著作 Major Publications |
・佐藤桃子編、永田祐・谷口郁美監修(2020)『子どもと地域の架け橋づくり 滋賀発子どもの笑顔はぐくみプロジェクトがつなぐ地域のえにし』全国コミュニティライフサポートセンター
・佐藤桃子(2020)「「子どもの貧困」をめぐる現状と地域における子ども食堂の意義」関耕平,宮本恭子,藤本晴久ほか『地域が抱える“生きづらさ”にどう向き合うか(山陰研究ブックレット9)』今井印刷,92-105. ・佐藤桃子(2021)「デンマークにおける児童保護サービスの動向」『社会福祉研究』第142号, 鉄道弘済会, 92-98. ・佐藤桃子(2022)「北欧におけるファミリー・グループ・カンファレンスの特徴と展開」『島根大学社会福祉論集』第8巻, 島根大学人間科学部福祉社会教室, 27-41. 佐藤桃子(2021)「第4章 仕切りを外すつながりづくり―地域の子ども食堂と学習支援の取り組みから」村上靖彦編『すき間の子ども、すき間の支援』明石書店,116-147. ・佐藤桃子(2023)「第11章 子ども家庭支援―フードバンクしまね「あったか元気便」の実践」斉藤弥生・ヴィクトール・ペストフ編『コ・プロダクションの理論と実践:参加型福祉・医療の可能性』大阪大学出版会,265-283. |
| より詳しい情報 More information |
Research map https://researchmap.jp/momokosato |
藤川信夫 Nobuo FUJIKAWA

| 研究概要 Research |
1)人生の歩みにおけるさまざまな節目において躓いたり立ち止まったりする人々と、その人生の歩みを支えようとする支援者たちの間で遂行される日常的相互行為を対象として、ドラマトゥルギー(演技論・演出論)的観点で質的フィールド研究を行っています。そうした相互行為からは、周囲を取り巻くモノや他者との、あるいは、自己自身の身体や過去の記憶との新たな共生のあり方を追い求める人々の姿を見て取ることができます。 2)人生の節目で行われる儀礼(あるいはその痕跡)とそれに関連する神話的言説の構造を分析することで、その儀礼の意味や機能を明らかにする神話学研究も行っています。1) From viewpoint of dramaturgy I study on various interactions of our everyday life concerning education and welfare. 2) Through analysis of rites of passage and mythical discourses I also carry out mythological study to clarify meaning and function of them. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
教育哲学、教育人間学 Philosophy of education, Anthropology of education |
| 研究キーワード Research Keywords |
ドラマトゥルギー、神話学、儀礼 Dramaturgy, Mythology, Rite |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・共生の人間学特講 ・共生の人間学特定演習 ・Philosophical Anthropology in Kyosei I ・Philosophical Anthropology in Kyosei Seminar I-b/II-b |
| 代表的な著作 Major Publications |
・藤川信夫 (2017)『人生の調律師たち-動的ドラマトゥルギーの展開』春風社
・藤川信夫 (2014)『教育/福祉という舞台』大阪大学出版会 ・藤川信夫 (2008)『教育学における優生思想の展開』勉誠出版 ・藤川信夫 (1998)『教育学における神話学的方法の研究』風間書房 |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=6660
Researchmap:https://researchmap.jp/read0068667 |
山崎吾郎 Goro YAMAZAKI

| 研究概要 Research |
新しい科学技術によって身体がどう変化するか、またそれにともなって社会の認識や構成がどう変化していくのか、その相互的なプロセスに関心があります。これまで、日本の臓器移植医療などをとりあげて、主に身体(body/corps)の変容に注目して研究を進めてきました。最近は、コミュニティという社会体(social body/corps social)の衰退や変容について考えながら、「近代」が想定してきた 基本的な概念をとらえなおすことに関心を寄せています。文化人類学が専門ですが、哲学や科学技術社会論といった関連する分野との交流や協働にも興味をもっています。
My research interest is in understanding the reciprocal processes of transformation between body and society, both from a theoretical and an empirical perspective. I work on an anthropological research concerning organ transplantation and some other medical practices. Currently, I also do research in shrinking communities where society (social body) transforms through depopulation. These interests have led me to collaborate with people from other disciplines such as philosophy, Science and Technology Studies, etc. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
文化人類学 Anthropology |
| 研究キーワード Research keywords |
身体と社会、自然、技術的環境、協働 body and society, nature, technological environment, collaboration |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・フィールド・プロジェクト ・課題解決ケーススタディ ・共生学実験実習 I ・Field Project ・Case Study for Problem Solving ・Laboratory in Kyosei Studies |
| 代表的な著作 Major Publications |
・山崎吾郎 (2018)「臓器提供の意思をどう示すか」『医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者』東洋経済新報社pp. 185-199.
・山崎吾郎 (2017)「消滅と無為の実践論:自然の人類学における翻訳の問題」『思想』1124: 92-104. ・山崎吾郎 (2015)『臓器移植の人類学―身体の贈与と情動の経済 』世界思想社 ・山崎吾郎 (2014)「意識障害をめぐる部分的な経験:療養型病院における生の人類学」『思想』1087: 89-105. ・Yamazaki, G. (2017) The Body with Anonymous Organs: Transformation of the Body and the Social in ・Yamazaki, G. (2013) From cure to governance: the biopolitical scene after the brain death controversy in |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=3397
Researchmap:https://researchmap.jp/read0152533 |
共生行動論
渥美公秀 Tomohide ATSUMI

| 研究概要 Research |
災害場面(救援、復旧、復興、防災)で活動する災害ボランティアと人・モノとの共生について、グループ・ダイナミックスの視点から、活動現場に参加して恊働的実践を行い、様々なアクションリサーチを展開して、明らかにしていきます。具体的には、緊急時の救援活動、被災地間の関係、災害体験の伝承、長期的な復興交流、地域防災の活性化といった活動の現場で災害ボランティア活動に参加しながら、背後にある社会・文化・歴史的背景に関する理論的考察を行い、現場の改善に寄与する研究を目指しています。国内では、熊本地震、東日本大震災、中越地震、阪神・淡路大震災などの被災地、海外では、台湾集集大地震などの被災地に注目しています。
Kyosei of disaster volunteers with people and things have been investigated from the perspective of group dynamics; collaborative practices followed by action research at various phases (i.e., search & rescue, recovery, revitalization, and preparedness) of disaster fields. We have attempted to contribute, academically and practically, to the betterment of the disaster field. We participate in disaster volunteer activities such as, for instance, disaster relief in an emergency, relaying supports from disaster fields in the past to the current fields, transferring and remembering experiences of disaster, long-term recovery and revitalization, and disaster preparedness in community. At the same time, we theoretically analyze their socio-cultural and historical backgrounds, Currently, we focus on domestic disaster fields after Kumamoto Earthquake, Great East Japan Earthquake, Niigata Chuetsu Earthquake, and Great Hanshin-Awaji Earthquake, as well as international disaster fields after Taiwan Chi-Chi Earthquake. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
グループ・ダイナミックス Group dynamics |
| 研究キーワード Research keywords |
グループ・ダイナミックス、災害、災害ボランティア、恊働的実践、アクションリサーチ Group dynamics, disaster, disaster volunteers, collaborative practice, action research |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・ボランティアの集団力学 ・ボランティア行動学演習 ・共生行動論特講 ・共生行動論特定演習 ・Group Dynamics of Volunteer Activities ・Seminar in Sciences of Volunteer Activities ・Socio-Behavioral Dynamics of Kyosei ・Seminar in Socio-Behavioral Dynamics of Kyosei |
| 代表的な著作 Major Publications |
・渥美公秀・貫牛利一(2021)『東日本大震災と災害ボランティア岩手県野田村、復興への道』大阪大学出版会
・渥美公秀・石塚裕子(2021)『誰もが〈助かる〉社会』新曜社 ・渥美公秀・稲場圭信(2019)『助ける』大阪大学出版会 ・渥美公秀(2014)『災害ボランティア—新しい社会へのグループ・ダイナミックス』弘文堂 ・渥美公秀(2001)『ボランティアの知』大阪大学出版会 ・宮前良平・置塩ひかる・王文潔・佐々木美和・大門大朗・稲場圭信・渥美公秀(2021)「実践としてのチームエスノグラフィ:2016年熊本地震のフィールドワークをもとに」『質的心理学研究』20, . ・渥美公秀(2021)「新型コロナウイルス禍後の社会に向けて2—2020年10月災害ボランティアを巡って」『災害と共生』4(2), 1-9. ・渥美公秀(2020)「新型コロナウイルス禍後の社会に向けて: 2020年4月」『災害と共生』,4(1),95-102. ・渥美公秀(2020)「尊厳ある縮退によるコミュニティの再生と創生:概念の整理と展望」『災害と共生』4(1),1-9. ・石塚裕子・渥美公秀(2020)「縮退時代のまちづくりに防災・減災を織り込む—兵庫県上郡町赤松地区におけるアクションリサーチ」『地区防災計画学会誌』18, 25-41. ・大門大朗・渥美公秀・稲場圭信・王文潔(2020)「災害ボランティアの組織化のための戦略実験」『社会心理学研究』60(1),18-36. ・渥美公秀(2020)「防災第3世代のインクルーシブ防災とは」『未来共創』7,67-81. ・寶田玲子・渥美公秀(2020)「在日外国人による災害支援活動と地域の互酬性ついての一考察: 在日外国人支援団体「シランダの会」事例より」『共生学ジャーナル』4, 172-188. ・渥美公秀(2020)「災害ボランティアの課題と展望」『21世紀ひょうご』28, 39-50 ・渥美公秀(2019)「〈助かる〉社会に向けた災害ボランティア」『災害と共生』3(1),49-56. ・Miyamae, R. & Atsumi, T. (2019). The Picturescue Movement: Restoring Lost Photographs Following the Great East Japan Earthquake and Tsunami, Disasters,44(1),85-102. ・山口洋典・渥美公秀・関嘉寛(2019)「メタファーを通した災害復興支援における越境的対話の促進-新潟県小千谷市塩谷集落・復興10年のアクションリサーチから」『質的心理学研究』18,124-142. ・渥美公秀(2019)「観光客(郵便的マルチチュード)としての災害ボランティア」『災害と共生』2(2), 9-14. ・大門大朗,渥美公秀(2019)「アメリカ社会科学の系譜と研究動向:災害研究センター(DRC)を中心とした歴史背景から」『災害と共生 』2(2), 15-40. ・林亦中・渥美公秀(2019)「四川大地震から10年を迎えて:四川地震10周年・芦山地震5周年被災地復旧・復興学術研究会および第2回(2018年)学校減災教育研究会を中心に」『災害と共生』2(2), 57-64. ・Atsumi, T., Seki, Y. & Yamaguchi, H. (2019). The Generative Power of Metaphor: Long-Term Action Research on Disaster Recovery in a Small Japanese Village. Disasters, 43(2): 355-371. ・Daimon, H., & Atsumi, T. (2018). Simulating disaster volunteerism in Japan:“Pay It Forward” as a strategy for extending the post-disaster altruistic community. Natural Hazards,Online first, 1-15. ・Daimon, H. and Atsumi, T.(2017) “Pay it forward” and Altruistic Responses to Disasters in Japan: Latent Class Analysis of Support Following the 2011 Tohoku Earthquake. Voluntus 29(1): 119-132 ・Atsumi, T. (2015) Against the Drive for Institutionalization: Two Decades of Disaster Volunteers in Japan.A. E. Collins, S. Jones, B. Manyena, & J. Jayawickrama (Eds.), Hazards, Risks, and Disasters in Society. Amsterdam: Elsevier, 19-32 ・Atsumi, T. (2014) Relaying Support in Disaster-Affected Areas: The Social Implications of a “Pay-it-Forward” Network. Disasters, 38(2), 144-156. ・Atsumi, T. & Goltz, J.D. (2014) Fifteen Years of Disaster Volunteers in Japan: A Longitudinal Fieldwork Assessment of a Disaster Non-Profit Organization. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 32(1), 220-240. ・Atsumi, T. (2009) Acceptance in a disaster area: process technologies for implementation scientists.Journal of Natural Disaster Science, 30, 97-103. |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=784
Researchmap:https://researchmap.jp/read0076469 |
宮本匠 Takumi MIYAMOTO

| 研究概要 Research |
災害復興について、実際の支援活動に加わりながら、内発的な復興がいかに可能なのかを研究してきました。とりわけ、外部支援者の受容的な役割に注目し、よりよい未来を描くことが困難な被災地において、どのように人々が自らの生の豊かさを支えるよりどころを再認識し、よりよい生を実現できるかに関心があります。研究手法としては、被災者に災害から現在までの出来事をあらわす曲線を描いてもらい、それを意味づけながらインタビューを行う復興曲線インタビューや、当事者自身が自らの生活や復興の様子について調査を行う当事者調査などを行っています。最近は、災害直後の災害ボランティア活動のあり方に着目し、現代社会におけるよりよい助けあい社会がいかに可能なのかについても研究を進めています。
I have been researching how endogenous recovery from disasters is possible while participating in actual relief activities. I am interested in how people in disaster-stricken areas, where it is difficult to envision a better future, can reconfirm the foundations that support the richness of their own lives and realize a better life, focusing on the receptive role of external supporters. My research methods include recovery curve interviews, in which survivors are asked to draw a curve representing events from the disaster to the present, and then interviewed while making sense of the curve, and surveys of the survivors themselves, in which they themselves are surveyed about their own lives and recovery. Recently, I have been focusing on the nature of disaster volunteer activities immediately after a disaster and studying how a better mutual aid society is possible in today’s society. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
グループ・ダイナミックス
Group Dynamics |
| 研究キーワード Research keywords |
災害復興、コミュニティ、内発性、当事者、アクションリサーチ
Disaster Recovery, Community, Action Research |
| 主な担当科目 Classes Taught |
共生行動論Ⅱ
Socio-Behavioral Dynamics of Kyosei |
| 代表的な著作 Major Publications |
・矢守克也・宮本匠 (2016).『現場でつくる減災学』新曜社 pp.163-186.
・宮本匠 (2021).「第2章インクルーシブを問い直す」 渥美公秀、石塚裕子『誰もが<助かる>社会-まちづくりに織り込む防災・減災』新曜社 pp.22-31. ・宮本匠 (2018).「第11章災害ボランティアと現代社会/第12章内発的な復興の主体形成」 室﨑益輝、冨永良喜『災害に立ち向かう人づくり-減災社会構築と被災地復興の礎』ミネルヴァ書房 pp.180-203. ・宮本匠 (2018).「第5章 災害復興のアクションリサーチ-内発的な復興のきっかけとなる5つのツール-」 草郷孝好『市民自治の育て方-協働型アクションリサーチの理論と実践-』関西大学出版部 pp.97-116. ・宮本匠 (2016).「16.アクションリサーチ」 北村英哉、内田由紀子『社会心理学概論』ナカニシヤ出版 pp.291-305. ・Tatebe,C.,and Miyamoto,T. (2021). Possible roles of People’s Organization for post-disaster community recovery: A case study on recovery process after Philippine Typhoon Yolanda. Progress in Disaster Science. 28. ・Kusago,T.,and Miyamoto,T. (2014). The Potential for Community-based Action Research for Area Studies: A Process Evaluation Method for the Improvement of Community Life. Psychologia. 57, pp.275-294. ・Miyamoto,T.,and Atsumi,T. (2011). Visualization of Disaster Revitalization Processes: Collective Constructions of Survivors’ Experiences in the 2004 Niigata Chuetsu Earthquake. Progress in Asian Social Psychology Series. 8, pp.307-323. ・Miyamoto,T.,and Atsumi,T. (2009). Creative Processes of Community revitalization using a Narrative Approach: A Case Study from Chuetsu Earthquake. Progress in Asian Social Psychology Series. 7, pp.259-275. |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/2c2d4ac4dfc35025.html?k=%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E5%8C%A0
Researchmap:https://researchmap.jp/7000010566 |
権藤恭之 Yasuyuki GONDO

| 研究概要 Research |
2000年から慶応義塾大学と共同で現在まで東京都23区の百寿者および全国の超百寿者の方達を対象に訪問面接調査を行ってきました。2010年より、東京都健康長寿医療センター研究所、慶応大学医学部と高齢者の縦断調査SONICを開始。現在、超高齢者を対象に健康長寿を達成するための要因を研究している。どうすれば超高齢期をしあわせにすごすことができるのか、その環境づくりに関心を持っています。
Yasuyuki Gondo is an associate professor of Osaka university department of human sciences since 2007. He started his carrier as gerontologist in 1993 by start working at the Tokyo metropolitan institute of gerontology. He got Ph.D. by papers about cognitive aging. He joyed Tokyo centenarian study in 1999. Since then he interviews more than 400 centenarians. He started larger epidemiological longitudinal study named (Septuagenarian, Octogenarian, Nonagenarian Investigation with Centenarian) with collaborators in multi-disciplinal researchers all over Japan in 2010. The main purposes of he SONIC study are to clarify aging-related changes in multiple domains of human functioning and the dynamics of interaction among these domains throughout the extreme old age period and to identify the factors influencing healthy longevity, including psychological well-being. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
高齢者心理学、老年学 Psychology of aging, gerontology |
| 研究キーワード Research keywords |
長寿、幸福、認知機能、加齢、社会関係資本 Longevity, well-being, cognition, aging, social capital |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・臨床死生学・老年学 ・Psychology of aging |
| 代表的な著作 Major Publications |
・Gondo, Y., Hirose., N., Yasumoto, S., Arai, Y., Saito, Y. (2017) “Age verification of the longest lived man in the world,” Experimental Gerontorogy.
・Gondo, Y., Maui, Y., Inagaki, H & Hirose, N. (2014) How do we measure cognitive function in the oldest old? A new framework for questionnaire assessment of dementia prevalence in centenarians. in Lars- ・Gondo, Y., Arai, Y & Hirose, N. (2014) Wellbeing in the Oldest Old and Centenarians in Japan.In T.B.L. ・Gondo, Y., Nakagawa, T., & Masui, Y. (2013) A New Concept of Successful Aging in the Oldest Old: ・Gondo, Y., & Poon, L.W. (2007) Cognitive function of centenarians and its influence on longevity.In
|
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=2357
Researchmap:https://researchmap.jp/ygondo 研究室HP:http://sonic-study.jp/ |
近藤佐知彦 Sachihiko KONDO

| 研究概要 Research |
英国でコミュニケーション論(修士)とディスコース分析(博士)を学び、構築主義の視点から社会心理学的な諸問題を分析してきました。現代人のアイデンティティ構築や、社会における正統性の獲得プロセス(例えば立憲君主制国での一般人の平等意識)などがメインのテーマになっています。本学では英語交換留学プログラムのコーディネーターが本務ですので、ディスコース分析に加えて留学生教育やグローバル人材育成教育も守備範囲に入ってきています。日本のような非英語圏大学における英語による専門教育の妥当性などについても論じる機会が増えてきました。大学国際化施策全般の批判的分析のかたわら、本学におけるその企画立案および実施に取り組むことも増えてきました。今はディスコースの手法を使いながら「国際化」の意味を問うていきたいと考えています。
Studied Communication (MSc) and Discourse Analysis (PhD) in the UK, Kondo has looked at social psychological subjects from constructionists’ point of views. Kondo has been hugely interested in the process of justifications of social realities amongst ordinary people (namely ideology), such as the idea of modern monarchism (Constitutional Monarchy). At Osaka University, working as a coordinator of an English speaking exchange program, Kondo also looks at International Student Education and Global Competency Education. He therefore researches some related topics, which includes tertiary education in English in non-English speaking countries. What is more, as a specialist of international student education, he plans and implements a number of university’s international strategies with several professors and administrators at Osaka. Kondo now dreams to focus on the meanings of internationalisation (and globalisation) of the education, using discursive techniques. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
ディスコース分析、社会心理学、留学生教育 Discourse Analysis, Social Psychology, International Student Education |
| 研究キーワード Research keywords |
イデオロギー、メディア、グローバル人材、大学国際化 Ideology, Media, Global Competency, University Internationalisation |
| 主な担当科目 Classes Taught |
|
| 代表的な著作 Major Publications |
・近藤佐知彦(2009)『天皇ヒロミチとその時代;逆説的天皇論の試み』晃洋書房
・Kondo, S. (2016) ‘Impact of the English Language on University Policy in Malaysia and Japan’ in T. |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=2216
Researchmap:https://researchmap.jp/read0076589 |
共生社会論
稲場圭信 Keishin INABA

| 研究概要 Research |
宗教的利他主義・社会貢献、市民社会のアクション・リサーチ、ソーシャル・キャピタルとしての宗教、宗教施設を地域資源とした地域防災に関する研究が主な研究テーマです。災害支援の仕組みとして、スマホやPCで使える「未来共生災害救援マップ」(http://www.respect.osaka-u.ac.jp/map/)も運営しています。グローバル化が進む今、現代社会と宗教は重要なテーマとなっています。私の研究室では、現代社会の諸問題に真摯に向き合い、宗教社会学や現代社会学の理論をベースに、支え合う市民社会の構築に資する学際的な研究を構想します。フィールドワークを重視し、研究方法としては質的調査を主とします。
Religious Altruism, Civil Society, and Religion as Social Capital.One of the organizers of the Japan Religion Coordinating Project for Disaster Relief, launched in response to the massive earthquake in northeastern Japan on March 11, 2011. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
宗教社会学 Sociology of Religion |
| 研究キーワード Research keywords |
宗教、利他主義、ソーシャル・キャピタル、災害支援、防災 Religion, Altruism, Social Capital, Disaster Prevention |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・共生社会論演習Ⅰ・Ⅱ ・共生社会論特講Ⅲ ・現代社会を読み解く 他 ・Social Sciences in Kyosei |
| 代表的な著作 Major Publications |
・稲場圭信 (2018)『アメリカ創価学会における異体同心─二段階の現地化』新曜社
・稲場圭信 (2016)『災害支援ハンドブック~宗教者の実践とその協働』春秋社 ・稲場圭信 (2013)『震災復興と宗教』明石書店 ・稲場圭信 (2013)『利他主義と宗教』弘文堂 ・稲場圭信 (2009)『社会貢献する宗教』世界思想社 ・稲場圭信 (2008)『思いやり格差が日本をダメにする~支え合う社会をつくる8つのアプローチ』NHK出版 ・Inaba, K. (2014) “Fostering civil society organizations for disaster relief in Japan “, in Minako Sakai,Edwin Jurriens, Jan Zhang and Alec Thornton eds.,Disaster Relief in the Asia Pacific, New York,Routledge, pp.52-66. ・Inaba, K. (2009) ‘Religion and Altruism’, in Peter B. Clarke ed., The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, Oxford University Press, pp.876-889. ・Inaba, K. (2006) The Practice of Altruism: Caring and Religion in Global Perspective, Cambridge Scholars Publishing. ・Inaba, K. (2004) Altruism in New Religious Movements: The Jesus Army and the Friends of the Western Buddhist Order in Britain, Daigaku Kyoiku Shuppan. |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=1050
Researchmap:https://researchmap.jp/altruism 研究室HP: |
福田 雄 Yu FUKUDA
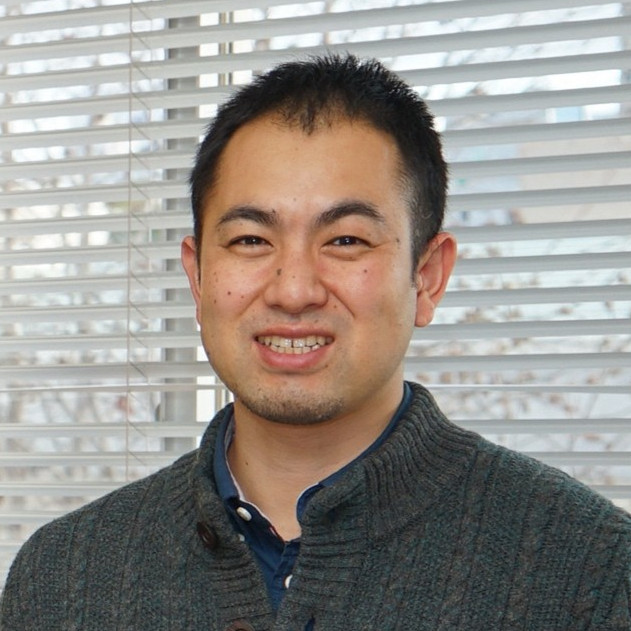
| 研究概要 Research |
災害や事故のあとに行われる慰霊祭や追悼式の調査研究をしてきました。主たる調査地は、東日本大震災やスマトラ島沖地震の被災地、そして長崎市です。フィールドワークや資料調査から得られたデータを、苦難とどう向き合うかという観点から考察しています。災禍の儀礼とよばれる記念行事のほか、災害遺構の比較調査、無形民俗文化財の三次元計測の研究もしています。
I have been researching memorial ceremonies after disasters, such as commemorations of the 2011 Great East Japan Earthquake and the 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunami. I examine data collected through fieldwork employing the perspective of suffering. In addition to studying post-disaster rituals, I have conducted comparative research on disaster remains and intangible cultural heritages. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
宗教社会学、災害社会学 Sociology of Religion, Sociology of Disaster |
| 研究キーワード Research Keywords |
災禍の儀礼、苦難の社会学 Post-disaster Ritual, Sociology of Suffering |
| 主な担当科目 Classes Taught |
地域共生学特定(特別)演習I Studies of Conviviality in Community: Master’s Seminar Studies of Conviviality in Community: Doctoral Seminar |
| 代表的な著作 Major Publications |
|
| より詳しい情報 More information |
研究者総覧:https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/d52938fde7169449.html
Researchmap: https://researchmap.jp/u_fkd |
グローバル共生学
国際協力学
杉田映理 Elli W. SUGITA

| 研究概要 Research |
途上国の安全な水と衛生(トイレ・手洗い・月経対処)に関する課題、社会開発との関連について研究しています。最近は、日本を含めた学校保健における衛生教育や月経をめぐる課題にも関心を持っています。研究のベースとしているのは、国際協力に文化人類学の知見を応用しようとする「開発人類学」であり、フィールドワークを通じて、現場の人々の生活や視点を知ることが大切だと考えています。
主な対象地域は、ウガンダ、ケニアを中心とする東部アフリカです。トイレや衛生教育、月経対処への関心から日本も研究対象にしています。 My research focus is on water, sanitation and hygiene (WASH) issues both in developing countries (particularly Africa) and in Japan. I have also started research on menstrual wellbeing and school health. Development anthropology forms the base of my research, applying cultural anthropology to regional and international development |
|---|---|
| 専門分野
Research Field |
開発人類学、月経研究、水・衛生分野の国際協力、アフリカ地域研究 Development Anthropology, WASH (water, sanitation & hygiene), Menstruation studies, African Studies |
| 研究キーワード Research keywords |
開発人類学、国際協力、村落給水、トイレ、月経、アフリカ(特にウガンダ)、日本 development anthropology, water supply, hygiene promotion, MHM (menstrual hygiene management), international cooperation, Uganda, Kenya, Japan |
| 主な担当科目 Classes Taught |
【学部】 ・国際協力学Ⅰ ・国際協力学演習Ⅰ、II(ゼミ) ・共生学の話題 【大学院】 ・国際協力学特講I ・国際協力学特定演習Ⅰ、II など・International collaboration and development studies I ・Seminar in international collaboration and development studies |
| 代表的な著作 Major Publications |
・杉田映理・新本万里子編著(2022)『月経の人類学 : 女子生徒の「生理」と開発支援』世界思想社
・杉田映理(2022)「水・衛生(WASH)の緊急人道支援—命と尊厳のための基本的ニーズ—」『緊急人道支援の世紀—紛争・災害・危機への新たな対応―』ナカニシヤ出版 ・杉田映理(2016)「子連れフィールドワーク:ウガンダへ」FENICSフィールドワーカーシリーズ第12巻『男も女もフィールドへ』古今書院 ・杉田映理(2011)「エミックな視点から見えるトイレの問題:現地社会の内側からの理解とは」『開発援助と人類学:冷戦・蜜月・パートナーシップ』明石書店 ・Sugita, E.(2022)Gender and Culture Matters: Considerations for Menstrual Hygiene Management. In The Sanitation Triangle: Socio-Culture, Health and Materials. Springer ・Sugita, E. (2021) Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Japanese Elementary Schools: Current conditions and practices. Pediatrics International, 64(1) e15062- ・Sugita, E. (2016) Comparison of Handwasihng Methods in Uganda: Is using a Tippy Tap better than washing hands using |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=10008784
Researchmap:https://researchmap.jp/read0155208 |
坂口真康 Masayasu SAKAGUCHI

| 研究概要 Research |
教育社会学・比較教育学を学問的基盤とし、グローバル化が進行する時代における「共生社会」と教育(特に学校教育)に関する研究に取り組んできました。特に、個人研究活動としては、既存の共生社会論や共生教育論の精緻化を行うために、南アフリカ共和国西ケープ州での現地調査に基づいた研究を実施してきました。他にも、共同研究活動として、日本の家庭科教科書における外国につながる人々やその暮らしの描写のされ方に関する言説研究等に従事してきました。中でも、アフリカの教育普遍化と格差に関わる比較研究などを通じて、日本国内外出身の研究者との国際共同研究活動を展開してきました。
現在までの研究活動で注力してきたのは、学問的営みとして共生社会や共生教育論の観点から現実の出来事を記述することに徹するのみならず、現実を生きる人々との関係性を重視することです。その中で、様々な背景の人々と共に、「共生」について考え、その実現を目指す上で障壁となっている出来事の解決策を協働で探索してきました。 Based on sociology of education and comparative education as academic disciplines, I have been conducting studies on ‘living together society’ and education (especially school education) in the era of globalisation. Specifically, as part of my personal study activities, I have been conducting studies based on field researches in the Republic of South Africa in order to refine the existing theories of living together society and education for living together. In addition, as part of my joint study activities, I have been engaging in discourse studies on how people who are connected to foreign countries and their lives are portrayed in Japanese home economics textbooks, etc. Particularly, I have been developing international joint study activities with researchers from Japan and abroad through comparative studies related to the universalisation of education and disparities in Africa, etc. What I have been focusing on in my study activities to date is not only to describe actual events from the perspective of theories of living together society and education for living together as an academic work, but also to value relationships with people who live in reality. By doing so, I have been thinking about ‘living together’ and working together with people with various backgrounds to explore solutions to the obstacles that stand in the way of realising it. |
|---|---|
| 専門分野
Research Field |
教育社会学・比較教育学
Sociology of Education & Comparative Education |
| 研究キーワード Research keywords |
共生社会論、共生教育論、南アフリカ共和国の学校教育、日本における外国につながる人々に関わる教育、学校教員の養成・研修
Theory of living together society, Theory of education for living together, School education in the Republic of South Africa, Education regarding people who are related to foreign countries in Japan, School teacher preparation and training |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・共生の理論と実践/Theory and Practice in Kyosei
・共生学の話題/Topics in Kyosei Studies ・共生学実験実習Ⅱ/Laboratory in Kyosei Studies Ⅱ ・国際協力学演習Ⅰ/Seminar in International Collaboration and Development Studies I ・国際協力学特定演習I/Seminar in International Collaboration and Development Studies I ・国際協力学特別演習I/Advanced Seminar in International Collaboration and Development Studies I |
| 代表的な著作 Major Publications |
・坂口真康(2021)『「共生社会」と教育――南アフリカ共和国の学校における取り組みが示す可能性』春風社.
・坂口真康・小川未空・アンドリアマナシナ ルズニアイナ ラスルナイヴ・園山大祐(2023)「中等教育カリキュラムと修了試験にみる「格差」概念の探索――南アフリカ、ケニア、マダガスカルの比較」澤村信英・小川未空・坂上勝基編『SDGs時代にみる教育の普遍化と格差――各国の事例と国際比較から読み解く』明石書店,pp.220-238. ・坂口真康(2022)「スポーツを通じた共生教育」小野雄大・梶将徳編『新時代のスポーツ教育学――Neo Sport Pedagogy and Andragogy』小学館集英社プロダクション,pp.126-135. ・坂口真康(2022)「南アフリカ コロナ禍の社会と学校教育――トップダウン式対策とボトムアップ式対策の往還」園山大祐・辻野けんま編『コロナ禍に世界の学校はどう向き合ったのか――子ども・保護者・学校・教育行政に迫る』東洋館出版社,pp.143-152. ・坂口真康(2018)「市民社会と学校教育の課題」吉田武男監修,飯田浩之・岡本智周編『MINERVA はじめて学ぶ教職6 教育社会学』ミネルヴァ書房,pp.67-79. ・坂口真康・岡本智周(2016)「「共生」にかかわる社会意識の現状と構造」岡本智周・丹治恭子編『共生の社会学――ナショナリズム、ケア、世代、社会意識』太郎次郎社エディタス,pp.224-241. ・坂口真康(2024)「南アフリカ共和国における教育の普遍化と格差の現状と論点――格差是正の対策・支援と「人間の尊厳」」『比較教育学研究』第68巻 pp.202-221. ・坂口真康・坂口(山田)有芸・山田文乃(2023)「日本の家庭科教科書における外国につながる人々やその暮らしの描写のされ方に関する考察」『中研紀要 教科書フォーラム』No.24,pp.36-48. ・坂口真康(2022)「南アフリカ共和国におけるグローバル化に関わる教育の一考察――高等学校段階のLife Orientationの教科書を事例として」『アフリカ教育研究』Vol.13,pp.42-53. ・Sakaguchi, Masayasu, Miku Ogawa, Andriamanasina Rojoniaina Rasolonaivo & Daisuke Sonoyama, 2021, “Exploring the Concept of ‘(In)equality’, ‘(In)equity’, and ‘(Dis)parity’ in the National Curricula and Examinations of Secondary Education: A Comparison Between the Cases of South Africa, Kenya, and Madagascar” 『アフリカ教育研究』Vol.12,pp.49-62. ・坂口真康(2021)「学校教育における「多様性」と「統一性」の折衷点に関する一考察――南アフリカ共和国西ケープ州の教育省行政官と学校教員の認識を事例として」『教育学研究』第88巻第4号,pp.671-683. ・坂口真康(2020)「「ナショナルな基準」と多様な実践の間で揺れる社会的な「共生」を志向する教育――南アフリカ共和国西ケープ州の高等学校段階の教員の認識を事例として」『教育社会学研究』第106集,pp.145-166. ・坂口真康(2019)「南アフリカ共和国の高等学校に通う学習者の「共生社会」志向に関する一考察――Life Orientation の学習経験による他者との関係の変化に着目して」『アフリカ教育研究』Vol.10,pp.63-77. ・坂口真康(2015)「南アフリカ共和国における「共生」のための教育に関する一考察――西ケープ州の高等学校を舞台とした認識のせめぎ合いに着目して」『比較教育学研究』第50号,pp.89-111. |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/71c645c7189e39f1.html
Researchmap:https://researchmap.jp/msaka |
伊東さなえ Sanae ITO

| 研究概要 Research |
文化人類学の視点から、国際協力が実際の支援対象地の人々にどのように受け止められ、展開しているのかについて研究しています。調査地は南アジア、特にネパールです。研究を始めたきっかけは青年海外協力隊員としてネパールで廃棄物処理に関するプロジェクトに携わったことでした。活動の中で、地域固有の状況と国際開発協力の言説の狭間で、自分たちなりに活動する現地の人々に出会い、その活動について研究するようになりました。2015年にネパールで大地震が発生し、調査していた村も大きな被害を受けたため、国際支援組織や調査村のコミュニティ組織と連携し、日本での募金活動や被災地でのボランティア活動を行いつつ、災害人類学的な調査も行うようになりました。
From a cultural anthropological perspective, I am researching the ways in which international cooperation is received and implemented by the people in the communities where it actually takes place. My study site is South Asia, particularly Nepal. I started my research when I was involved in a waste management project in Nepal as a Japan Overseas Cooperation Volunteer (JOCV). Since the earthquakes in 2015, from which severely damaged my study site, I have been conducting disaster anthropological research in parallel with relief activities in cooperation with international aid organizations and community organizations in my study village. |
|---|---|
| 専門分野
Research Field |
文化人類学、南アジア地域研究、環境社会学 Cultural Anthropology, South Asian Area Studies, Environmental Sociology |
| 研究キーワード Research keywords |
災害、都市環境問題、NGO、地域、国際協力、南アジア、ネパール Disaster, Urban Environment, NGO, Locality, International Collaboration, South Asia, Nepal |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・共生学の話題/Topics in Kyosei Studies ・共生学実験実習Ⅱ/Laboratory in Kyosei Studies Ⅱ ・国際協力学演習Ⅰ/Seminar in International Collaboration and Development Studies I ・国際協力学特定演習I/Seminar in International Collaboration and Development Studies I ・国際協力学特別演習I/Advanced Seminar in International Collaboration and Development Studies I |
| 代表的な著作 Major Publications |
伊東さなえ (2024)『ネパール大震災の民族誌―共同性と市民性が交わる場で災害に対応する―』ナカニシヤ出版.
伊東さなえ (2017)「ネパール・カトマンドゥ盆地におけるハムロ・空間の表出―廃棄物をめぐる実践の事例から―」『南アジア研究』, 29, pp.6-32. Ito, S. (2019). A Polycentric Waste Management System in the Kathmandu Valley, Nepal, Journal of Environmental Science and Sustainable Development (JESSD), 2(1), pp.61-74. 伊東さなえ (2019)「ネパール・カトマンドゥ盆地における震災下のローカリティの生産―瓦礫と祭りの関係に着目して―」『アジア・アフリカ地域研究』, 19(1), pp.1-27. (第5回環境社会学会奨励賞(論文の部)受賞作品) Ito, S. (2020). The Production of Locality through Debris and a Festival: Aftermath of the Gorkha Earthquake in the Kathmandu Valley. Studies ㏌ Nepali History and Society, 25(2), pp.363-383. 伊東さなえ (2023).「コミュニティ・レジリエンスが発揮される空間―ネパール2015年地震で被災した都市近郊農村を事例として―」『環境社会学研究』, 29, pp.87-103. |
| より詳しい情報
More information |
Researchmap:https://researchmap.jp/ito-s |
地域創生論
大谷順子 Junko OTANI, DDS, MPH, MS, PhD

| 研究概要 Research |
グローバル化する現代社会において、健康、エイジング、教育、少数民族、環境、食の安全、国内格差、災害などの切り口を含め、国際協力・ 社会開発学、国際保健・人口学、社会政策学、社会学、ジェ ンダー、オリンピックなどの視点から、地域研究を行います。研究対象地域は中国や中央アジアのシルクロード地域に限らず、カンタベリー地震が発生したニュージーランド、またオーストラリアやアメリカなどの研究者らとの国際共同研究も行っています。方法論の確立はもとより、英語、中国語をはじめ研究対象地域の言語の習得も重視し、現地調査を伴うアプローチが奨励されます。世界銀行や世界保健機関(WHO)など国際機関勤務の経験を生かし、学際的研究を行います。
In a globalizing society, the transformation of China into a regional superpower has a great influence not only on local geopolitical order in Asia but also on international society. China’s economic growth and world-leading aging population have created a challenging policy, public provision, and global diplomacy environment. In this context, we explore various social issues, including population demographics, health, environment, food safety, information/censorship, disaster impacts (Sichuan earthquake for example), Olympics, as core areas of study. Associated with these issues are multi-disciplinary considerations such as international relations, social development studies, international health and population, social policy, political science, sociology, gerontology, and gender studies. Our research area is not limited to China, however, and we perform international collaborative investigations with researchers from New Zealand, Australia, United States, Europe, and the Central Asian Silk Road area. We place importance on rigorous research methodology, and encourage our researchers to obtain supplementary language skills to support research, including proficiency in English, Chinese and other languages and emphasize an importance on field work and cultural competence. |
|---|---|
| 専門分野
Research Field |
国際保健・人口学、老年学、母子保健、地域研究、国際社会開発、国際災害社会学、研究方法論 Population and Global Health, Gerontology, Maternal and Child Health, Area Studies, International development studies, Disaster Research, Research methodology |
| 研究キーワード Research keywords |
子育て、キャリア育て、ワークライフバランス、レジリエンス、中国、中央アジア、ニュージーランド、オーストラリア China, Central Asia, New Zealand, Australia, resilience, work life balance, child rearing |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・地域創生論 ・地域創生論特講 ・地域創生論特定演習 ・Area Studies |
| 代表的な著作 Major Publications |
・大谷順子 編(2023)『子育ても、キャリア育ても―ウィズ・ポストコロナ時代の家族のかたち』九州大学出版会
・大谷順子 編(2021)『四川大地震から学ぶ復興のなかのコミュニティと「中国式レジリエンス」の構築』九州大学出版会 ・大谷順子( 2016)「高等教育グローバル化に目覚めた中国――大学の国際化と海外拠点の活動を通して」(第7章)『世界大学ランキングと国際評価を問う』京都大学学術出版会 ・大谷順子(2015)「アートによる創造的復興の企て-保険に支えられた移動/再建 2011ニュージーランド」(第9章299-326頁)『新しい人間、新しい社会――復興の物語を再創造する』災害対応の地域研究シリーズ第5巻 京都大学学術出版会 ・大谷順子(2010)『人間科学のための混合研究法―質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン』北大路書房(翻訳) (原著 John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, Sage.) ・大杉卓三・大谷順子(2010)『人間の安全保障と中央アジア』花書院 ・大谷順子(2007)『国際保健政策からみた中国―政策実施の現場から』九州大学出版会 ・大谷順子 (2006/2015新装版) 『事例研究の革新的方法―阪神大震災被災高齢者の五年と高齢化社会の未来像―』九州大学出版会. ・Otani, Junko (Ed.) (2023). Reconstructing Resilient Communities after the Wenchuan Earthquake: Disaster Recovery in China, Lexington Books: Rowman & Littlefield. ・Cavaliere, Paola & Otani, Junko (Eds.) (2024). Handbook of Disaster Studies in Japan, MHM Limited & Amsterdam University Press. ・Otani, Junko (2014). ‘An ageing society and post-disaster community security’, (Chapter 8), In: Paul Bacon and Christopher Hobson (eds.), Human Security and Japan’s Triple Disaster: Responding to the 2011 Earthquake, Tsunami and Fukushima Nuclear Crisis, Routledge, pp. 127-140. ・Otani, Junko (2012 ). ‘Ageing Society, Health issues, Assessing 3/11’(Chapter 14), In: Jeff Kingston(ed.) Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan, Oxford University Nissan Institute/ Routledge Japanese Studies Series, London: Routledge/ Taylor and Francis Group, pp.237-254. ・Otani, Junko (2010). Older People in Natural Disasters, Kyoto University Press & Melbourne: Trans Pacific Press. ・Otani, Junko (2009 ). ‘Elderly survivors of the 1995 Great Hanshin Earthquake in Japan: NVivo application to Japanese field research’ In: Methods in Practice, Lyn Richards (ed) (eBook) Sage: London, 2009.04 www.sagepub.co.uk/richards or www.uk.sagepub.com/richards ・Otani, Junko (2010). Older People in Natural Disasters: The Great Hanshin Earthquake of 1995. Kyoto University Press & Trans Pacific Press, 2010 |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧 : https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/acc55cc58b8cef91.html Researchmap : https://researchmap.jp/read0209505 研究室HP : https://areastudies-hus-osaka-u-ac-jp.jimdofree.com |
コンフリクトと共生
MOHACSI Gergely モハーチ ゲルゲイ
| 研究概要 Research |
日本を主な調査地として、病気をめぐる文化、身体、科学技術との相互作用を研究しています。病院、実験室、患者会など、多種多様な医療現場において2003年からフォールドワークを積み重ねることにより、慢性病の増加に伴う身体感覚の変容について探求してきた。またここ最近は、調査範囲をハンガリーと東アジアに広げて、薬用植物の栽培および研究開発を調べ始めています。創薬に焦点をあてることで、未来を生み出そうとする多様な実践に内在する人間および動植物の共生を描き出し、また伝統医療と近代医療との交差から見えてくる、比較方法の新たな可能性を探ります。
Gergely MOHÁCSI is a medical anthropologist with special interest in science and technology studies and comparative ethnography. His research has focused on the embodied interactions betweenscience, medicine and society in contemporary Japan, most notably in the domain of diabetes self-care. He conducted fieldwork in hospitals, laboratories and patient groups in Japan and Hungary. Currently, he is investigating the co-constitution of things and values in the development and use of herbal medications in Japan and Southeast Asia. By highlighting the entanglement of different medical traditions and the multispecies interactions between medicinal plants and humans in the process of producing new medications, he aims to explore the new possibilities and challenges of ethnographic comparison. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
文化人類学、科学技術の人類学、医療人類学、日本・東アジア研究 cultural anthropology, anthropology of science and technology, medical anthropology, Japanese and East Asian Studies |
| 研究キーワード Research keywords |
比較方法、病気、薬草、身体論、planetary health comparative method, disease, medicinal herbs, embodiment, planetary health |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・人類学ⅠAnthropology I ・コンフリクトと共生演習I・Ⅱ Seminar in Conflict and Coexistence Studies ・コンフリクトと共生特講 I・ⅡResearch Seminar in Social and Cultural Theory ・Research Seminar in Social and Cultural Theory ・人新世の世界 The World of Anthropocene |
| 代表的な著作 Major Publications |
・モハーチゲルゲイ (2017)「薬物効果のループ—西ハンガリーにおける臨床試験の現場から」『文化人類学』81(4):614–631頁
・モハーチゲルゲイ・今井貴代子(2016)「共生と多文化―比較の展望」『未来共生学』3:11–212頁 ・モハーチゲルゲイ (2011)「病気の通約—血糖自己測定の実践における現実としての批判」『現実批判の人類学―新 ・Mohácsi Gergely (ed.) (2014) Ecologies of Care: Innovations through Technologies, Collectives and the Senses. Readings in Multicultural Innovation, Vol. 4. Osaka: Doctoral Program for Multicultural ・Mohácsi Gergely(2013)The Adiponectin Assemblage: An Anthropological Perspective on ・Mohácsi Gergely (2011) Commensurating Disease: Self-measurement of Blood Glucose as a Form of Criticism, In Naoki Kasuga, ed. pp.203–224., Anthropology and the Critique of Reality. Kyoto: Sekaishisō . |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=10000746
Researchmap:https://researchmap.jp/mohacska |
太田貴大 Takahiro OTA
| 研究概要 Research |
人と自然との共生を、生態系サービス(自然の恵み)という視点から、研究しています。生態系サービスは、人と自然との関係を幅広くカバーしており、食料供給や水源涵養から、美しい景色を見て幸せになるという精神的な便益まで多岐にわたります。そのため、自然科学・社会科学・人文学のアプローチを統合して、学際的な研究を目指しています。現在、興味を持っているのは、養蜂やアナツバメの巣採取といった自然環境に依存する農業、生態系サービスを維持するための仕組みや環境政策、伝統文化や食文化と健康、狩猟における人と鳥獣との多様な関係、ボードゲームを使った地域の環境問題解決などです。人科の敷地内で養蜂と園芸を実践しています。海外のフィールドは、インドネシアやカンボジアです。 |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
自然共生論、生態系サービス論 |
| 研究キーワード Research Field |
ミツバチ、アナツバメの巣、淡水魚生食、森林環境税、水田稲作、里海、カモ網猟、ボードゲームデザイン |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・コンフリクトと共生Ⅱ「生態系サービス論」・共生学の話題「自然環境と人間との共生」
・コンフリクトと共生演習Ⅰ |
| 代表的な著作 Major Publications |
・太田貴大 (2021) ポリネーターが生産する供給サービスの受益者評価: 長崎市市街地産の百花蜜に注目して. 環境共生. 37 (1). 65-69,
・太田貴大 (2021) 地方自治体の森林整備費における住民一人当たりの税負担額の概算: 長崎県を事例に. 九州森林研究. 74. 43-46. ・Donkersley, P., Covell, L., & Ota, T. (2021) Japanese Honeybees (Apis cerana japonica Radoszkowski, 1877) May Be Resilient to Land Use Change. Insects. 12(8). 685. ・太田貴大, 高田雅之 (2020) 生態系の文化サービスにおける文化的遺産価値の危機レベル評価: 自然環境と関係の深い長崎県指定文化財を事例として. 環境情報科学論文集. 34. 311-316. ・Ota, T., Kusin, K., Kilonzi, F.M., Usup, A., Moji, K., & Kobayashi, S. (2020) Sustainable Financing for Payment for Ecosystem Services (PES) to Conserve Peat Swamp Forest Through Enterprises Based on Swiftlets’ Nests: An Awareness Survey in Central Kalimantan, Indonesia. Small-Scale Forestry. 19(4). 521-539. ・Kilonzi, F.M. & Ota, T. (2019) Influence of Cultural Contexts on the Appreciation of Different Cultural Ecosystem Services Based on Social Network Analysis. One Ecosystem. 4. e33368. ・太田貴大 (2018) 怪異・妖怪伝承データベースを用いた計量分析の試み: 伝承呼称数と島嶼環境特徴の関係性に注目して. 環境共生. 33. 25-30. ・太田貴大, 上原拓郎, 桜井良, 仲上健一 (2016) きれいで豊かな海の経済価値: 広島湾北東部の海水浴場とカキ養殖の事例. 政策科学. 23 (4). 99-120. ・太田貴大, 上原拓郎 (2014) 効果的な生態系サービスへの支払い(PES)設計のための3つの政策研究課題と注意点. 環境経済・政策研究. 7 (1). 63-66. |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/76d7ac63b61fa5f0.html |
佐伯いく代 Ikuyo SAEKI
| 研究概要 Research |
私は、人が豊かな生活を送りながらも、自然やほかの生き物と共存できる方法を知りたいと考えています。そのためには、①自然の特徴や仕組みを理解すること、②それと調和していくための方策を考えること、の二つのアプローチがあり、その両方について保全生態学や共生学の観点から研究を進めています。
I like to know how people can live with nature in a sustainable way. There are basically two approaches: 1) understanding ecological characteristics and processes of natural ecosystems, and 2) develop social systems balancing between conservation and utilization of nature. My research focuses on both approaches based on the perspectives from conservation biology and human-environment coexistence. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
保全生態学 人と自然との共生学
Conservation biology; Coexistence studies between people and nature. |
| 研究キーワード Research keywords |
生態系、生物多様性、保全、人と自然との関係
Ecosystem; Biodiversity; Conservation; linkages between people and nature |
| 主な担当科目 Classes Taught |
共生学の話題:生物多様性と自然共生
Biodiversity and coexistence of people and nature コンフリクトと共生II:社会と環境のサステイナビリティ Sustainability of society and environment |
| 代表的な著作 Major Publications |
Saeki, I., S. Hioki, W. A. Azuma, N. Osada, S. Niwa, A. T. Ota, and H. Ishii. 2024. Legacy over a thousand years: Canopy soil of old-growth forest fosters rich and unique invertebrate diversity that is slow to recover from human disturbance. Biological Conservation 292: 110520. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110520.
Saeki, I. and Y. Li. 2022. Restoration contributes to maintain ecosystem services and bio-cultural linkages between wetlands and local communities: a case from a botanical diversity hotspot in Japan. Wetlands Article No. 117. https://doi.org/10.1007/s13157-022-01639-2 Saeki, I., A.S. Hirao, T. Kenta, T. Nagamitsu, and T. Hiura. 2018. Landscape genetics of a threatened maple, Acer miyabei: Implications for restoring riparian forest connectivity. Biological Conservation 220: 299-307. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.01.018 佐伯いく代.2012. 生物多様性とエコシステムマネジメント-生態系を基軸とした保全と管理.『エコシステムマネジメント‐包括的な生態系の保全と管理へ』(森章編)p278-p293. 共立出版. |
| より詳しい情報
More information |
Researchmap:https://researchmap.jp/read0112289 |
山田一憲 Kazunori YAMADA
| 研究概要 Research |
ヒトや動物がどの様に生き、どの様に死んでいくのかに興味があります。彼ら/彼女らの生き様は、種や集団や個体によって違っている一方で、共通している点もみられます。最近は、勝山ニホンザル集団(岡山県真庭市)と淡路島ニホンザル集団(兵庫県洲本市)を対象とした比較研究を行い、それぞれの集団に見られる行動特性の違いが神経伝達関連遺伝子の多型と関連しているのかどうかを調べています。特に、淡路島のニホンザルは、特異的に寛容な攻撃性の低い社会を形成していることが明らかになっています。社会の多様性がどのような理由で生じるのか(文化や遺伝的背景)、それによって個体の生き方がどのように変わっていくのかを発達的に検討したいと考えています。
The goal of my research is to investigate the roots of human sociality.I work with the free-rangingJapanese monkeys (Macacafuscata) in japan. We can be aware of the evolutionary similarity between human and nonhuman primates through field observation of their social behaviors. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
比較行動学、発達心理学、霊長類学 Ethology, primatology, and developmental psychology |
| 研究キーワード Research keywords |
行動、葛藤、社会的発達、適応進化、寛容性 Behavior, social conflict, social development, adaptive evolution, tolerance |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・コンフリクトと共生特講I・Ⅱ ・コンフリクトと共生特定演習I・Ⅱ ・比較行動学 ・霊長類心理学 ・比較行動学演習I・Ⅱ ・ヒトと動物の行動学 ・心理・行動科学入門 ・Conflict and Coexistence StudiesI・II ・Conflict and Coexistence Studies: Masters Readings Seminar I ・Ethology ・Primate Psychology ・Seminar in EthologyI・II ・Human and animal behavior ・Introduction to Psychology and Behavioral Science |
| 代表的な著作 Major Publications |
・山田一憲(2016)「霊長類のコンフリクトと共生」『共生学が創る世界』大阪大学出版会, 196-208頁
・山田一憲(2015)「霊長類における毛づくろいと利他行動」『未来共生学』2: 63-82頁 ・山田一憲(2012)「ニホンザルの個性は何から生まれるのか」『日本のサル学のあした―霊長類研究という「人間学」の可能性』京都通信社 72-77頁 ・KATSU, YAMADA, & NAKAMICHI (2016) Function of grunts, girneys and coo calls of Japanese ・UENO, YAMADA, & NAKAMICHI (2015) Emotional states after grooming interactions in Japanese ・YAMADA & NAKAMICHI (2006) A fatal attack on an unweaned infant by a non-resident male in a |
| より詳しい情報
More information |
研究者総覧:http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?l=ja&u=3251
Researchmap:https://researchmap.jp/read0156462 |
共生学系共通
Fanantenana Rianasoa ANDRIARINIAINA ファナンテナナ リアナスア・アンドリアリニアイナ

| 研究概要 Research |
I am exploring how young people in sub-Saharan Africa move from education to work with the rapid expansion of secondary education. I am particularly interested in understanding the role of family in the school to work transition process in rural and urban Madagascar. Recently, I have been exploring different areas such as higher education, education funding, and the role of the local community in school management. I mainly conduct fieldwork at school and in the community in Madagascar but recently, I was exploring the slum areas of Nairobi and the rural area of Kajiado in Kenya. |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
Comparative and international education, education and international development |
| 研究キーワード Research Field |
School to work transition, parental involvement, development, Madagascar |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・Topics in Kyosei Studies : Bridging Volunteerism, Education, and Philosophy ・A Door to Academia : Introduction to Comparative and International Education ・Laboratory in Kyosei Studies I |
| 代表的な著作 Major Publications |
・Andriariniaina, Fanantenana Rianasoa and Sawamura, Nobuhide. 2024. Community Involvement in School Management in Madagascar: Government Policies and School Practices. Journal of Kyosei Studies 8:184–199.
・Andriariniaina, Fanantenana Rianasoa. 2022. Parental Involvement in School to Work Transition in Rural Madagascar: Focusing on Parents’ Expectations of Education Outcomes. Journal of Kyosei Studies 6:1–22. ・Andriariniaina, Fanantenana Rianasoa, Ratompomalala, Harinosy and Sawamura, Nobuhide. 2021. Exploring the Changes Brought by Emergency Distance Education in Malagasy Universities: Disparities Under COVID-19 at a Teacher Training Institution. Africa Educational Research Journal 12:85–98. ・Andriariniaina, Fanantenana Rianasoa and Sawamura, Nobuhide. 2021. Investigating School to Work Transition in Rural Madagascar: Upper Secondary School Students’ Career Plans and Their Decision Patterns. Journal of International Development Studies 30(2):113–127. ・Andriariniaina, Fanantenana Rianasoa. 2017. The Trajectory of Children in the Rural Areas of Madagascar: Aspirations and Opportunities from School to Work. Africa Educational Research Journal 8:129–145. ・アンドリアリニアイナ, ファナンテナナ リアナスア・ラスルナイヴ, アンドリアマナシナ ルズニアイナ・園山大祐 2023「マダガスカル農村部における学校から仕事への移行―社会経済的地位による家族の意思決定に着目して―」澤村信英・小川未空・坂上勝基編『SDGs時代にみる教育の普遍化と格差―各国の事例と国際比較から読み解く―』pp. 87–108、明石書店。 ・アンドリアリニアイナ, ファナンテナナ リアナスア・澤村信英 2023「マダガスカルの大学における緊急的な遠隔教育による格差の生成―コロナ禍の教員養成課程学生の日常に着目して―」澤村信英・小川未空・坂上勝基編『SDGs時代にみる教育の普遍化と格差―各国の事例と国際比較から読み解く―』pp. 320–339、明石書店。 ・アンドリアリニアイナ, ファナンテナナ リアナスア・澤村信英 2019「マダガスカル農村部における子どもの就学から就業への軌跡―生徒の志望と就職機会に着目して」澤村信英編『発展途上国の困難な状況にある子どもの教育―難民・障害・貧困をめぐるフィールド研究』pp. 327–349、明石書店。
|
| より詳しい情報 More information |
研究者総覧:https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/81240a07726adb6e.html Researchmap:https://researchmap.jp/andriariniaina |
小泉空 Sora KOIZUMI
| 研究概要 Research |
第二次世界大戦後のフランス哲学、いわゆる「フランス現代思想」、「ポストモダン哲学」を、主に社会・政治的関心から研究しています。 その一方で、もう少し広く「社会哲学」なるもの、純粋哲学でも社会学でも批評でもないが、それらすべてに架橋するような分野がどのようにして可能になるのか、日々模索しています。 |
|---|---|
| 専門分野 Research Field |
フランス現代思想、社会哲学、メディア論 |
| 研究キーワード Research Field |
ポール・ヴィリリオ、ジャン・ボードリヤール |
| 主な担当科目 Classes Taught |
・社会哲学入門 ・実験実習I |
| 代表的な著作 Major Publications |
・「居住不可能なところに住むこと:ヴィリリオの空間論」『人間社会学研究集録』(12) 3-22 2017年3月
・「はかなきものたちのために――ジャン・ボードリヤールの 68 年論――」『年報カルチュラル・スタディーズ』 8 83-100 2020年7月 ・「壊れた世界とサイバネティックス――一頭馬車、ウィーナー、加速主義」『現代思想』 52(10) 2024年6月 |
| より詳しい情報 More information |
Researchmap:https://researchmap.jp/sorakoizumi |


